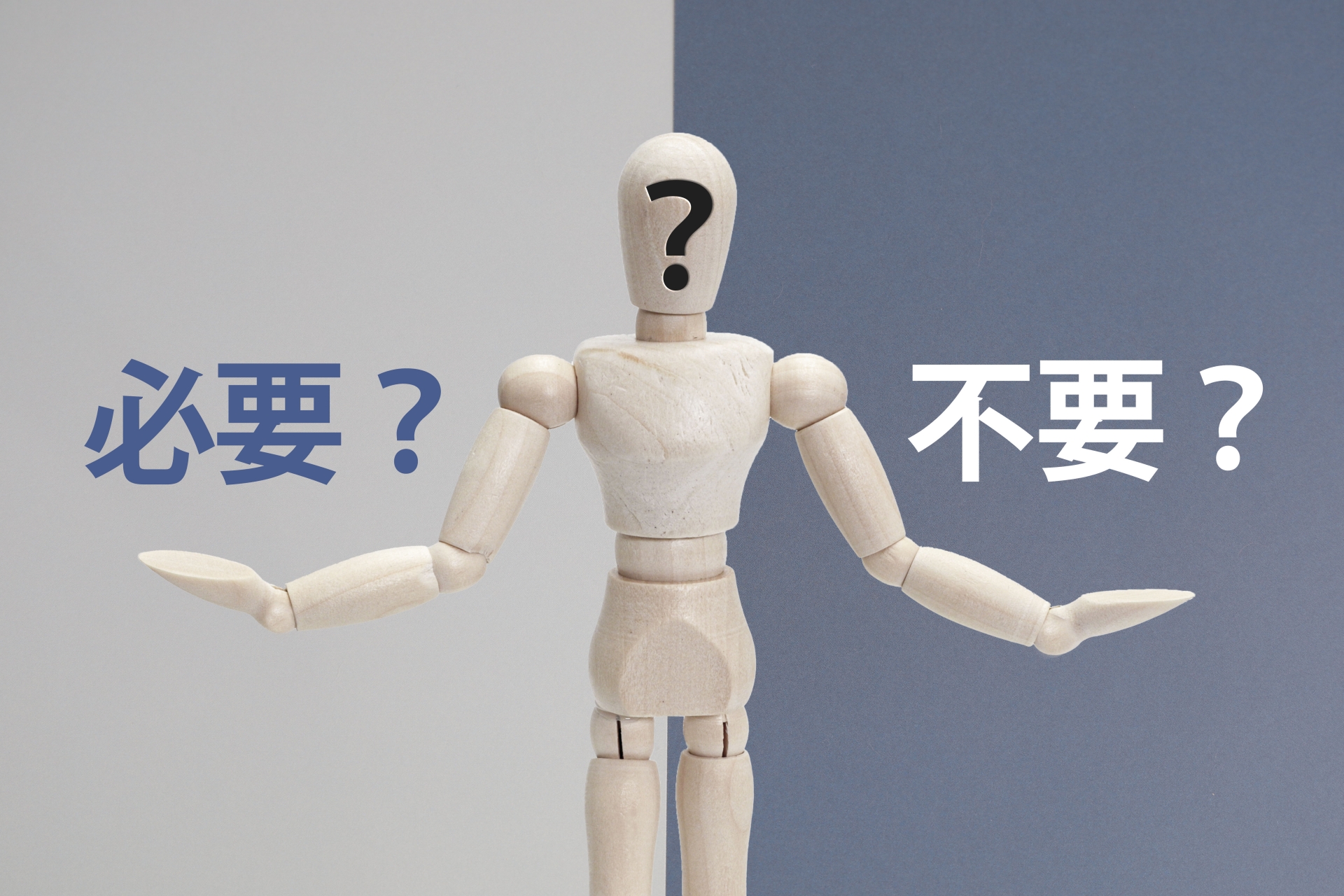
相続税申告が不要かどうかの判断は、ご自身で大まかには行うことができます。
もし被相続人(亡くなった方)の相続財産の総額が基礎控除額より少なければ、申告する必要はありません。
しかし、相続財産に不動産や株式などの有価証券などがある場合には判断がより難しくなるため、注意が必要です。
申告不要だと思っていても「みなし相続財産」や「名義預金」などを考慮し忘れ、期限後に実は申告が必要だったと判明する場合も少なくありません。
また、相続税には税額が軽減される特例や控除があり、それらを適用する場合には、基礎控除以下でも申告が必要な場合もあります。
そこで今回は、相続税申告が本当に不要かどうかを確認するための計算方法や注意すべき点を相続専門の税理士が詳しく解説していきます。
結論!相続税が基礎控除以下でも申告が必要な場合がある
相続税には「基礎控除」があり、相続財産総額がこの基礎控除額を下回る場合には、相続税額が0円となるため相続税の申告は不要です。
基礎控除とは、「どんな人でも、相続財産が一定の金額以下なら非課税=相続税0円」とされる非課税枠のことです。
しかし、相続税額が非課税=相続税0円でも税務署への申告が必要な場合があります。
それは、基礎控除額以上の財産総額があるが、特例や控除を使用すると相続税額が0円になる場合です。
少し難しい話になるので、順を追って分かりやすく解説していきます。
相続税の基礎控除の計算方法
基礎控除額は、法定相続人の数によって決まり、以下の計算式により算出します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人とは、被相続人の配偶者と血族のことを言い、家族であれば誰でも該当するというものではありません。
血族には以下のような優先順位があり、最も順位の高い人のみが法定相続人となります。
【血族の優先順位】
①第一順位:被相続人の子またはその代襲相続人(孫等)
②第二順位:被相続人の直系尊属(父母)
③第三順位:被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)
※法定相続人の中に「相続財産を全く受け取らない人」や「相続放棄をした人」がいた場合でも、法定相続人の人数に含めて計算します。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額は高くなっていくため、相続税はかかりにくくなります。
(例)法定相続人2人の場合は、基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
法定相続人5人の場合は、基礎控除額:3,000万円+600万円×5人=6,000万円
相続税の課税対象となる相続財産の総額とは?
課税対象となる相続財産の総額は、プラスの財産(不動産資産、金融資産など)からマイナスの財産(借入金、ローン残高、葬式費用など)等を引いた額となります。
相続財産の総額を計算するための財産リストは、こちらの記事で詳しく解説しています。
参照はこちらhttps://www.namikawa-kaikei.com/declare-yourself/
相続税が基礎控除以下でも申告が必要な場合って?
相続税を計算した結果、相続税額が非課税=相続税0円の場合は申告は不要となります。
相続財産総額 < 基礎控除額 なら相続税申告不要ということですね。
相続財産総額が基礎控除額より大きい場合は、もちろん申告が必要になりますが、「特例や控除」を使うことにより相続税が0円になる場合があります。
相続税が0円なら申告はしなくていいのでは?と思われるかもしれませんが、中には相続税申告が「特例や控除」の適用要件とされている「特例や控除」があります。
相続税申告書を提出しなければ、特例や控除そのものを適用できないということです。
そのため、「特例や控除」を考慮した結果0円になったからと言って、相続税申告をしないで期限が過ぎてしまった場合は、税務署側では「特例の適用なし」という判断となりますので「無申告加算税」と「延滞税」いう罰金を追加で払わなければいけなくなる可能性があります。
相続税申告が必要な特例や控除の種類

上記で説明した相続税の申告が適用要件とされる「特例や控除」にはどのようなものがあるか、具体的に詳しく解説していきます。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
被相続人の配偶者が相続した金額が、1億6,000万円(もしくは法定相続分)以下であれば配偶者には相続税が課税されないという特例です。
配偶者にとても有利な制度であり、法定相続分以下であればたとえ3億円でも課税されません。
ただし、配偶者控除を適用して、その配偶者や相続人全体の相続税額が0円(非課税)になったとしても、相続税の申告は必要です。
この制度を利用するには、その他にも法的な婚姻関係にあることや、申告期限までに遺産分割を終えていることなどが要件となります。
ただし、この特例を適用すれば配偶者にかかる相続税額が0円になる場合がほとんどですが、配偶者と他の相続人との間の遺産分割のバランスを考えて適用しないと将来その配偶者が亡くなった場合、子供への税負担が増すことになる可能性もあるので注意が必要です。
小規模宅地等の特例
被相続人や同一生計親族の居住用や事業用として使用している宅地等(土地や敷地権)について、一定の要件を満たせば、その宅地等の評価額を最大80%減額できる特例です。小規模宅地等の特例を適用して、相続税の課税価格が基礎控除額以下になる場合でも、相続税申告は必要です。
この小規模宅地等の特例は適用要件が複雑であることから、特例の適用を検討される方は、必ず相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。
農地の納税猶予の特例
相続で農地を取得した人が所定の要件を満たすと、農地にかかる税金の納税が猶予される特例です。
名称には「猶予」とありますが、実際には納税が免除される場合が少なくありません。
農地の納税猶予の特例があるのは、農地を相続した人に多額の相続税が課せられてしまうと、農地を売却しなければ納税できなくなり、引き続き農業を営めなくなる可能性があるためです。
この特例を受けるためには、農地などの納税猶予額や利子税の額に見合う価値がある担保を準備したうえで、相続税を申告しなければなりません。
また、申告書には相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類などを添付する必要があります。
国などに寄付した財産の非課税の特例(寄付金控除)
相続税の申告期限までに相続した財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合は、その財産は特例により相続税の課税対象になりません。
この特例を適用するときは、相続税の申告書に特例の対象になる財産の明細を記載し、寄付先による一定の受領書、証明書類などを添付する必要があります。
相続税申告が不要な特例や控除の種類
以下の「特例や控除」は相続税の申告をせずに適用することが可能です。
つまり、これらの「特例や控除」を使うことにより相続税が0円になる場合には相続税の申告が不要ということになります。
- みなし相続財産の非課税枠
- 障害者控除
- 未成年者控除
- 相次相続控除
相続税申告不要な場合
財産総額が相続税の基礎控除額以下の場合は、相続税がかからないため申告は不要です。
したがって、相続税申告が不要だと判断する前提として、
法定相続人の数を正しく把握して基礎控除額を正確に計算する事とともに、
不動産や株式などの有価証券も含めて財産の価値をできるだけ正確に把握して財産総額を正しく認識することが重要になります。
下記では、財産総額を認識するうえで間違いやすい点について解説していきます。
本当に財産総額が基礎控除額以下であるかを正確に確認しましょう。
ご自身で判断を迷われる場合は相続に強い税理士相談してみましょう。

注意点①みなし財産
みなし相続財産とは、本来なら民法上の相続財産といえないものの、相続が開始されたことで相続人が取得するお金のことを指します。
分かりやすい例では、死亡保険金や死亡退職金等です。
生命保険金・死亡退職金にはそれぞれ非課税枠があり、それぞれ「500万円×法定相続人の数」です。
非課税枠で差し引いた残りの部分をプラスの相続財産へ加え、相続税額を計算します。
(例)死亡保険金3,000万円、法定相続人が3人である場合
死亡保険金のうち「500万円×3人=1,500万円」が非課税枠、残りの1,500円は相続財産に加えます。
相続人以外の人が取得した死亡保険金や死亡退職金等には非課税の適用はないのでその点も注意しましょう。
注意点②名義預金
例えば、被相続人の名義ではないものの、実際にはその通帳の原資が被相続人から拠出されており、その通帳の維持管理や運用も被相続人が行っていた場合には被相続人の財産、つまり名義預金とみなされることがあります。
(例)
被相続人が子や孫の将来の為に貯蓄している子供や孫名義の口座
被相続人が相続税対策として作った配偶者や子供の名義の口座
専業主婦なのに残高が被相続人の夫よりも多い、または同額の妻名義の口座
注意点③相続時精算課税制度を利用した贈与財産
相続時精算課税制度とは、原則「60歳以上の両親や祖父母」から、「18歳以上(※)の子供や孫」に対して生前贈与した際に選択できる贈与税の制度のことです。
(※:贈与が令和4年(2022年)3月31日以前の場合は20歳以上です。)
相続時精算課税制度を利用する場合、最大2,500万円までの財産に贈与税はかかりません。
ただし、贈与された財産の額を相続財産の額と合算して相続税額の計算をしなければなりません。
注意点④相続開始前3年以内の贈与財産
暦年贈与(年間110万円以下)を利用してから3年以内に贈与者が亡くなった場合、その暦年贈与は無かったものと判断され、相続財産とみなされます。
ただし、相続財産とみなされるのは、相続人に対して行われた贈与のみとなります。
「養子や代襲相続人ではない孫」や「子の配偶者」などへの暦年贈与については、相続財産としてみなされないため、相続財産の額と合算する必要はありません。
なお税制改正により、上記の「3年以内」という期間は、令和9年(2027年)1月1日以降の相続から段階的に「7年以内」まで延長されます。
必要なのに、相続税申告をしなかったらどうなるのか

相続税申告が必要であるにも関わらず、相続税申告書の提出をしなかった場合、加算税や延滞税などの罰則が課せられます。
相続税の申告書を提出せず、税務調査が入って無申告を指摘されたり、財産の仮装・隠ぺいが認められたりすると、課せられる罰則が重くなってしまいます。
まとめ

以上、相続税申告が必要な場合、不要な場合について解説してきました。
どちらにせよ、まずは正確な相続財産の総額を算出することがとても大切です。この判断を間違えてしまうと、本来納めなくてもよいはずの税金を余分に納めることになってしまうので注意が必要です!
もし相続税申告不要かどうかご自身で判断が難しい場合には、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
当事務所は相続専門の税理士事務所です。
無料相談も承っておりますので、まずはぜひお気軽にお問い合わせください。
無料相談を実施しています
お気軽にご連絡ください
TEL:0120-93-8899
(平日・土曜9:00~18:00)
※お伺いした情報を外部に漏らすことはいたしません。
※営業のお電話は固くお断りします。

